私たちの暮らしの中で使われる言葉の中には、建築用語が語源のものが結構たくさんあります。
ここではそんな言葉をまとめてみました。
「几帳面」
「几帳」というのは、平安時代以降、公家の邸宅に使われていた間仕切りの一種です。
几帳の柱の表面は丸く面取りされており、両側に刻み目が入った細工が施されていました。
本来、その細工のことを「几帳面」といいます。
細部まで丁寧に仕上げられていることから、転じて、「きちんとしたさま」を表すようになりました。
「大黒柱」
大黒柱とは、伝統的な民家建築において、建物の中央に位置する柱のことですが、大黒柱は、地震が多い日本の建物を支える柱です。
最も太い柱に全部の梁をかけ、家の重みを支えるようにしたのです。
この最も太い柱をが転じて家の象徴となり、それを支える人のことを指すようになりました。
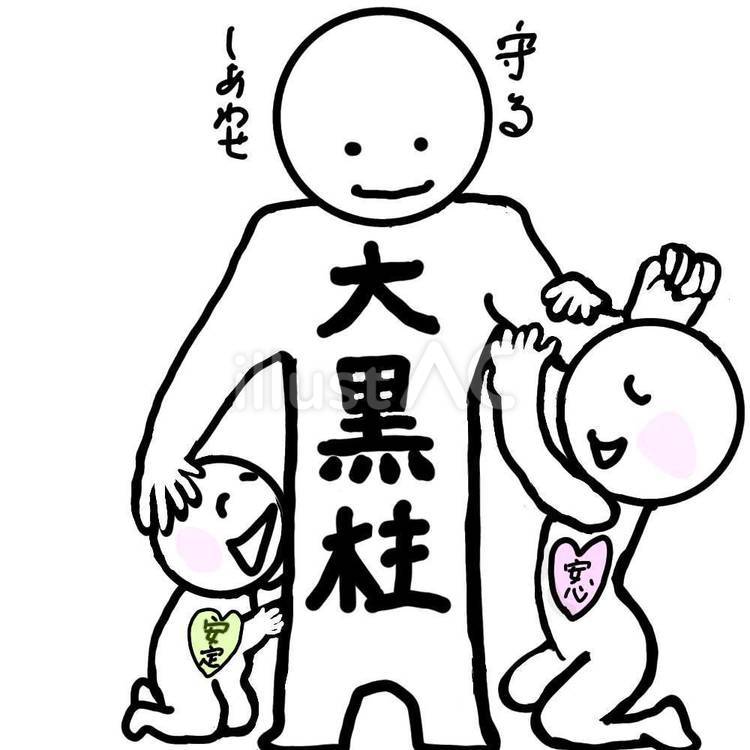
「子はかすがい」
子どもがいなければ夫婦が崩壊してしまうかもしれないさまを例えた言葉で、子どもに対する愛情が夫婦としての縁をつなぎとめてくれるという意味です。
かすがいは、2本の木材をつなぎ合わせる時に打ち込む大きな釘のことです。
コの字型をしており、ちょうど巨大なホチキスの針のようなものです。
「かすがい」は二つのものをつなぎとめるものから上記のような意味が生まれました。

「束の間」
「束」というのは長さの単位で、時間の短さを表す言葉として使われるようになりました。
建築でも、短い柱のことを「束」といいます。
「いの一番」
「いの一番」というのは、一番最初にする、という意味です。
「いの一番」とは、家を建てるときに最初に柱を建てる位置のことを指します。
柱の配置は「番付」というもので決められており、横方向はい・ろ・は…で、縦方向は一・二・三…となっています。
基礎ができて最初に柱を立てるのは、「い」の「一番」⇒「いの一番」なのです。
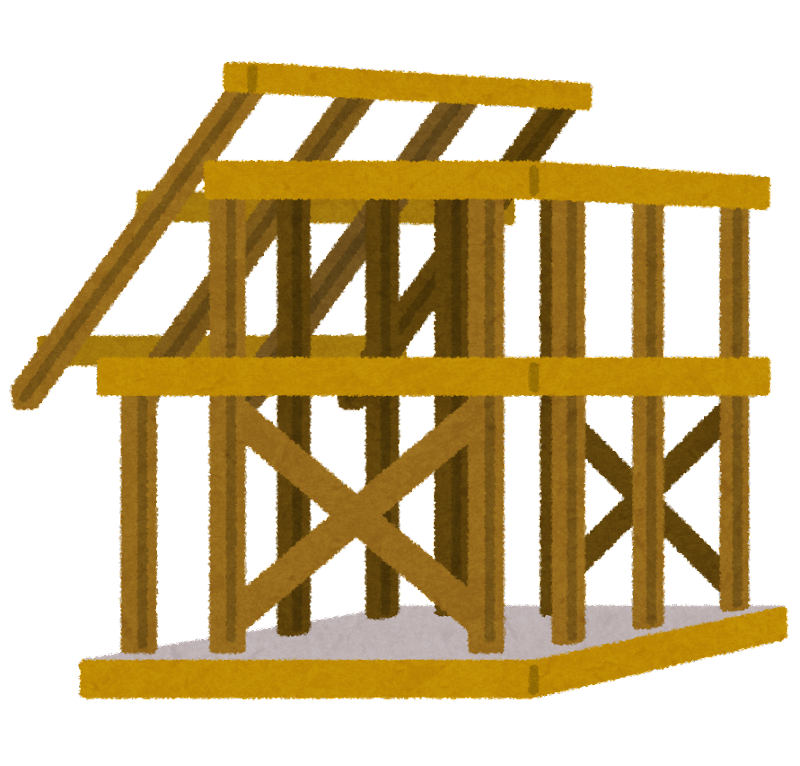
「うだつが上がらない」
「うだつ」とは、昔、隣家との境に設けられた袖壁のことです。
ひしめき合って建っていた町は火事になると延焼してしまうので、それを防ぐために、「うだつ」を防火壁として立てるようになったのです。
この防火という本来の目的以外に、次第に装飾として流行りはじめ、とくに商人たちが競い合って豪華な「うだつ」を建てるようになり、なかなか出世できず、地位が上がらず、生活が向上できず、豪華なうだつを立てられないさまを、「うだつが上がらない」と表現するようになりました。
「らちがあかない」の「らち」
「埒(らち)」というのは、囲いや仕切りのことです。この囲いや仕切りがあると、なかなか思うようにものごとが進まず、途中で止まっているような状態のことを「らちがあかない」というようになりました。
ほかにも「埒」を使ったものに「不埒(ふらち)」という言葉があります。
つまり法や道徳にはずれ、道理がないという意味で、「不埒な行い」などというように使います。
「たたき上げ」
「たたき」は「叩き」ではなく、「三和土(たたき)」が語源です。
これは、三種類の材料を混ぜて練り、叩きかためることから「三和土」と書かれるようになりました。
この叩き方が生半可だと良い土間にならないといわれたことから、下積み時代の苦労を経て一人前になることを「たたきあげ」というようになりました。

「ぼんくら」
「盆蔵」から来ているというものです。
土蔵というものは空気が乾燥している冬に建てるのが普通で、夏に建ててしまうと、土の表面ばかり乾燥して平均的に乾かず、役に立たない土蔵になってしまうと言われます。
つまり「盆の時期」に建てられた蔵が使いものにならないことから、ダメな人のことを「ぼんくら」というようになったというものです。
「羽目をはずす」
「羽目」とは、建物に平らに張られた板張りのことです。
せっかくきれいに張られた「羽目をはずす」と、建築としての意匠が台なしになってしまいます。
このことから、調子に乗って度を超すようなふるまいを「羽目をはずす」というようになりました。
いかがでしたか。
このほかにも、本当にたくさんの住まいの言葉が、現代の日本で普通に使われています。
言葉の語源をたずねることは楽しいものです、色々調べてみると、家づくりの勉強にもなります。




